2025年7月17日、任天堂からNintendo Switch 2向けに発売された『ドンキーコング バナンザ』は、シリーズの中でも異彩を放つタイトルとして注目を集めています。発売前から話題にのぼっていた本作は、従来の3Dアクションの枠を飛び越え、「破壊」というコンセプトを軸に据えた、まったく新しいタイプのゲーム体験を提供しています。
ドンキーコングといえば、長らく任天堂を象徴するキャラクターの一人として親しまれてきましたが、今回の『バナンザ』ではその魅力がさらにパワーアップしています。これまで以上に“力強さ”が前面に出たドンキーのアクションは、ただ走ったりジャンプするだけでなく、地形そのものを拳で壊して進んでいくという豪快なプレイが可能です。このゲームにおいて「壊すこと」は単なる演出ではなく、ゲーム進行の中核を担うメカニクスとして成立しており、ここが本作最大の特徴でもあります。
また、開発はもちろん任天堂自身が手掛けており、グラフィックや操作性といった細部に至るまで緻密に作り込まれています。Nintendo Switch 2という新ハードの性能をフルに活かした映像表現も相まって、圧倒的な没入感がプレイヤーを包み込みます。
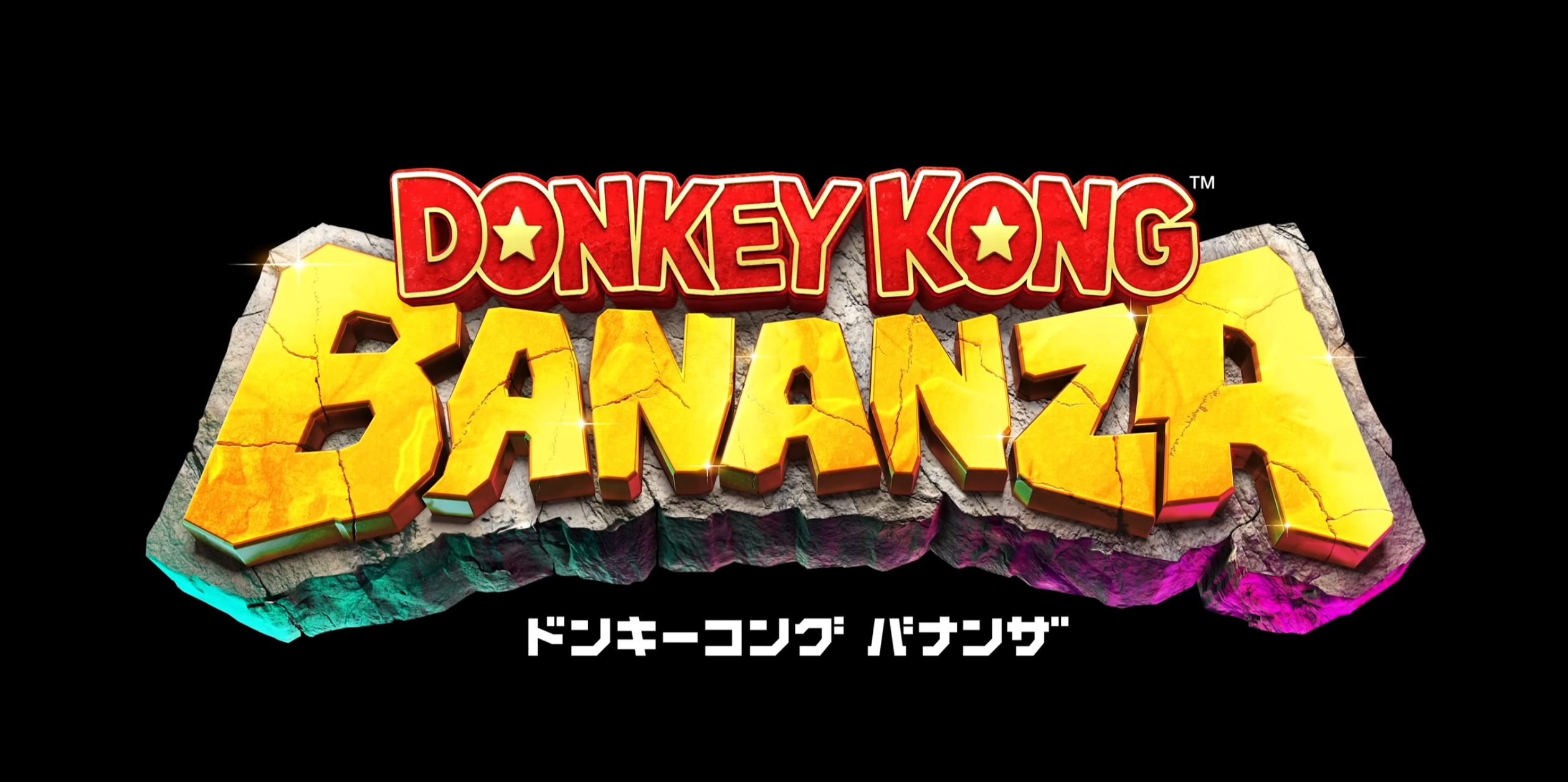
ゲームの舞台となるのは、広大で立体的に構成された地下世界です。そのスケールの大きさには思わず息をのむほどで、シリーズファンはもちろん、初めてドンキーコングに触れる人にも強烈な印象を与えることは間違いありません。
発売当日には多くのゲームメディアがレビューを一斉に公開し、その評価も軒並み高得点ばかりでした。中でもIGN Japanでは10点満点という快挙を達成しており、「Nintendo Switch 2初のキラータイトル」としての呼び声も高まっています。発売前に寄せられていた期待を上回る完成度に仕上がっており、単なるファン向けの続編というよりは、3Dアクションゲーム全体を進化させる革新的な作品として位置づけられているのです。
ゲームジャンルとシステムの革新性
本作『ドンキーコング バナンザ』が他のアクションゲームと一線を画している最大の理由は、そのゲームシステムの革新性にあります。単なる3Dプラットフォーマーとしての体裁を取りながら、コアメカニクスに「破壊」を据えることで、これまでの常識を根底から覆すようなプレイ体験が実現されています。
プレイヤーはドンキーコングを操作しながら、目の前に立ちはだかる壁や障害物、さらには床や天井までをも自由自在に破壊して進んでいきます。ただの破壊ではなく、パンチ一発で岩を砕き、拳で地面をえぐって地下へと突き進むなど、そのアクションには説得力とダイナミズムが同居しており、操作している側の感覚まで高揚してくるほどです。

もちろん、この破壊行動が単なる爽快演出にとどまらないという点も見逃せません。壊すことで新たなルートが開かれたり、隠された部屋が出現したりするなど、ステージの構造そのものがプレイヤーの行動に応じて変化していく仕組みになっています。つまり、「どこを壊すか」がそのまま攻略に直結しているというわけです。
特に興味深いのは、この破壊が“探索”と“謎解き”の両方に作用している点です。たとえば、一見すると行き止まりに見える場所も、地面を壊すことで思わぬ地下ルートが出現する場合があり、プレイヤーは常に「この先に何かあるかもしれない」というワクワク感を抱きながら行動することになります。まさに、環境そのものと対話しながら進む感覚が味わえる構造です。
さらに本作では、単に正解ルートをなぞるのではなく、プレイヤーのひらめきや実験的な破壊が新たな発見につながるよう設計されています。そのおかげで、一本道の退屈さとは無縁のプレイ体験が広がっており、何度でも繰り返し遊びたくなるような“再発見”の余地がたっぷりと用意されているのです。
このように『ドンキーコング バナンザ』は、従来のジャンルに属しながらも、その枠組みを押し広げるような革新的設計によって、プレイヤーに新たなゲームの楽しみ方を提示してくれます。それはもはや“ジャンルを超えた一作”と呼ぶにふさわしい完成度であり、アクションゲームに新しい風を吹き込む存在として注目されるのも納得というしかありません。
巨大な地下世界を舞台にした探索要素
プレイヤーが足を踏み入れるのは、地上とはまったく異なる巨大な地下世界。そのスケールは圧倒的で、ただ広いだけでなく、縦にも横にも層が重なり合い、まるで迷宮のように入り組んだ構造をしています。ステージごとに雰囲気も変化していき、古代の遺跡が眠るエリアや、光る鉱石に彩られた空洞、湿気と緑が入り混じった地下植物園のようなエリアまで、バリエーションに富んだ世界が広がっています。

こうしたステージ設計の中で、プレイヤーは単にゴールを目指すだけでなく、あらゆる場所に隠された“何か”を探すという探索要素にも夢中になるはずです。その筆頭が、ゲーム内で重要なコレクション要素となる「バナモンド」です。このバナモンドは、地形の破壊によって現れることも多く、何気なく壁を壊したり床を砕いたりしたときに、思いがけず現れることがあるため、まさに発見の喜びが詰まっています。
加えて、隠された“化石”の存在も本作ならではの楽しみの一つです。これらはただのアイテムではなく、特定のチャレンジをクリアすることでしか手に入らないものもあり、やりこみ要素としても機能しています。つまり、探索は一度通った道を戻る価値を生む仕掛けにもなっていて、単なる一本道ではなく、プレイヤーの視点や試行錯誤によって結果が変わってくるようになっています。
また、ゲーム内には“遺跡チャレンジ”と呼ばれる特殊なステージも点在しており、そこでは通常のフィールド以上に、アクションの正確さや発想力が求められます。足場が崩れる中での連続ジャンプ、特定の順番でオブジェクトを破壊するパズル的なギミックなど、ただ壊すだけでは突破できない仕掛けが用意されているので、プレイヤーは思わず「どうすれば先に進めるのか」と頭をひねることになるでしょう。
こうした探索要素の魅力は、単にアイテム集めに留まらず、世界そのものと“対話”していくような体験へとつながっています。ドンキーコングの腕力によって世界が壊れ、そこから新しい景色が姿を現す——この感覚がプレイヤーに強烈な没入感を与え、ゲーム全体の印象を一段と豊かなものへと押し上げているのです。
プレイアブルキャラ紹介:ドンキーコングとポリーン
『ドンキーコング バナンザ』では、シリーズの主役であるドンキーコングに加えて、なんとポリーンもプレイアブルキャラクターとして登場します。この組み合わせが実にユニークで、ゲームプレイの幅を大きく広げる要素となっているんです。どちらのキャラクターも個性が際立っていて、それぞれの能力がゲームの中で明確に役割を持たされている点がとても印象的です。
まずドンキーコングは、その見た目どおり圧倒的なパワータイプとして設計されています。岩壁を拳で砕いたり、床を叩き割って地下へ潜ったりと、まさに“破壊”を象徴する存在です。その動きには重みと説得力があり、一撃一撃のアクションには快感すら感じられます。操作していて非常に爽快ですし、彼のアビリティがそのままルート開拓やバトル、探索に直結しているため、プレイヤーの手ごたえとしてもしっかり伝わってきます。

一方でポリーンは、ドンキーコングとは真逆のアプローチを取るキャラクターとして登場します。彼女が持つのは“歌”という特殊な能力で、力では突破できないような場面でその真価を発揮する場面が多く用意されています。たとえば特定のギミックを作動させたり、周囲の敵の行動を変化させたりといった演出がなされており、彼女の登場によってゲームの戦略性がぐっと増しているのを感じます。
しかも、この2人の切り替えや協力によって生まれるプレイ体験が非常に魅力的なんです。一方が道を切り開き、もう一方がその道の先で知恵を使って謎を解く。そんな場面が自然と用意されていて、プレイヤーは力と知恵のコンビネーションを駆使しながらステージを攻略していくことになります。その構造がしっかりとゲームデザインに落とし込まれているため、単なるキャラクターの違いではなく、“遊び方そのものが変わる”という感覚があるんです。
また、2人プレイにも対応している点も見逃せません。ドンキーコングとポリーンをそれぞれが担当することで、息の合った連携プレイが楽しめますし、協力がうまくハマったときの達成感はひとしおです。家族や友人と遊ぶ場面では、このコンビシステムがコミュニケーションのきっかけにもなるはずですし、協力型アクションゲームとしてのポテンシャルも感じさせてくれます。
このように、ドンキーコングとポリーンという異なる能力を持つ2人のキャラクターが用意されていることで、『バナンザ』は単調さとは無縁の多彩なゲーム体験を提供してくれます。ただ壊すだけでは終わらない。その先にある知恵との連動が、この作品の奥行きと完成度を高めているのだと、プレイしているうちに自然と実感するはずです。
協力プレイ対応!2人で楽しめる爽快アクション
一人でも圧倒的に楽しい『ドンキーコング バナンザ』ですが、2人で遊んだときに広がる体験は、また別の魅力を帯びてきます。本作はローカルでの2人プレイに対応しており、ドンキーコングとポリーンをそれぞれが操作することで、ゲームの面白さがさらに加速していくんです。
ここで注目すべきは、ただの“同時プレイ”にとどまらないという点です。2人のキャラクターは能力の方向性がまったく異なっているため、自然と役割分担が生まれ、プレイヤー同士の連携が求められるようになります。例えば、ドンキーコングが岩壁を壊して道をつくったあと、その先にあるスイッチをポリーンの“歌”で起動させる。そんなやり取りが、テンポよく繰り返されていくんです。

このとき、お互いに声をかけ合ったり、どちらが先に動くかを相談したりと、自然とコミュニケーションが生まれます。それがこのゲームにおける“協力”の面白さであり、まるで二人で一つの冒険をしているかのような一体感を味わうことができます。プレイヤー同士の距離感を近づけるという意味でも、この設計は本当によく練られていると感じさせられます。
しかも、2人プレイだからといって難易度が緩くなるわけではありません。むしろ、連携が取れないと突破できないギミックや、タイミングを揃えないとクリアできないチャレンジもあり、緊張感と達成感のバランスが非常に良いんです。上手く連携が決まったときの気持ちよさは格別で、「もう一回やろう」と思わず言いたくなるほどの没入感があります。
また、協力プレイだからこそ見えてくる“相方の視点”というのも、このゲームの魅力のひとつです。普段なら自分のキャラクターしか見ていない場面でも、2人で遊ぶことで、相手がどういう動きをしているのか、どこに注目しているのかを知ることができ、それが新たな発見につながることもあります。同じステージでも、1人で遊ぶときとは異なる攻略法や感動に出会える可能性があるというのは、実に贅沢な設計だと感じました。
つまり『バナンザ』は、協力プレイを単なる“おまけ”ではなく、一つの完成された体験として組み込んでいるんです。誰かと一緒に楽しみたいゲームを探している人には、これ以上ない選択肢のひとつと言えるかもしれません。
レビュー・評価まとめ|IGN満点の理由とは
発売直後から『ドンキーコング バナンザ』は、国内外を問わず数多くのゲームメディアやプレイヤーから高く評価されてきました。特に象徴的なのが、IGN Japanで満点となる「10/10」のスコアを獲得したという事実です。この満点評価が決して話題性やブランド力だけによるものではないことは、レビュー本文を読めばすぐにわかります。
IGNのレビューではまず、「操作するだけで楽しい」という本質的な魅力に言及されています。ドンキーコングの動きにはひとつひとつに重みがあり、ボタンを押した瞬間に画面が“応えてくれる”ようなフィードバックの心地よさがあります。スティックを倒して走り、拳を振り下ろせば地面が揺れるような感覚が伝わってきて、まさにキャラクターと一体になっている感覚が味わえるんです。

また、レビュー内で特に強調されていたのが、「破壊可能な環境がただのギミックにとどまらない」という点でした。壊すことで道が開けたり、隠されたエリアが出現したりするのは先に述べたとおりですが、その全体の設計が“パズル”として成立していることが、プレイ中の知的満足感にもつながっていると評価されていました。つまり、ただ暴れるだけでは進めない。けれど力任せでも楽しい。この絶妙なバランスこそが、本作の革新性を支えている大きな要素だと感じさせられます。
さらにIGNでは、「Nintendo Switch 2の性能を生かしきった表現力」にも言及されていました。視覚的な迫力はもちろんのこと、サウンドや振動といったフィードバックの部分も細部まで丁寧に作り込まれており、ハードの世代交代にふさわしいフラッグシップ的な存在感があると断言されています。特に破壊の瞬間の演出や、地下世界の光と影のコントラストには驚かされる部分が多く、その没入感の深さがゲーム体験全体を押し上げているのは明らかです。
そしてこれは、専門メディアに限られた評価ではありません。海外の掲示板Redditや国内のSNS、ECサイトのレビュー欄などでも、「気づいたら何時間も遊んでいた」「久しぶりに時間を忘れて没頭した」といった声が多数寄せられています。遊びごたえがあるのに理不尽さは感じず、難易度の調整も絶妙。ゲームを離れたあとも、「またやりたい」と自然に思わせる中毒性があるという声も多く見られます。
こうして見ていくと、『ドンキーコング バナンザ』が単なるシリーズ最新作にとどまらず、アクションゲームというジャンル全体に新しい可能性を提示する作品として、多くの人に受け入れられていることがよくわかります。その評価が“満点”として表れたことには、何の違和感もありません。それほどまでに、このゲームが持つ完成度と革新性は圧倒的なんです。
総評|『ドンキーコング バナンザ』はSwitch 2のキラータイトルになるか?
ここまでご紹介してきたように、『ドンキーコング バナンザ』はあらゆる面において極めて完成度の高い作品に仕上がっています。任天堂が本気で新時代の3Dアクションを作り上げようとした意志が、ゲームの隅々にまで息づいており、プレイヤーはその熱量を自然と感じ取ることができます。
まず、“破壊”というテーマを軸に据えた設計が実に秀逸です。これまでのアクションゲームでは、“壊せる”という要素はあくまで演出やアクセントとして用いられることが多かったですが、本作ではそれがゲームデザインの中核に組み込まれています。破壊することで道が開け、謎が解け、探索が進む。その一連の流れがスムーズに連動していて、ゲームプレイに心地よいリズムが生まれています。
加えて、キャラクターの魅力とシステムの融合も本作の大きな強みになっています。力強さを全面に押し出したドンキーコングと、柔らかな知性を宿すポリーン。この2人が持つ異なる個性が、ただの操作キャラの違いではなく、“遊び方そのものの選択肢”として機能している点が素晴らしいんです。一人でじっくり攻略を楽しむも良し、二人でわいわい協力しながら突破していくも良し。それぞれのスタイルにフィットする柔軟さがあるからこそ、幅広いプレイヤーに受け入れられているのだと感じます。

そしてなにより、“遊んでいて気持ちいい”という感覚が、本作全体を貫いています。操作しているだけで楽しい。壊すたびに爽快感がある。進むたびに新しい景色と驚きがある。この積み重ねが、プレイヤーの没入感をどこまでも深めていきます。いくらビジュアルが美しくても、どれだけ話題性があっても、結局「遊んで楽しいか」がゲームの本質であるということを、この作品は改めて思い出させてくれました。
現時点で『バナンザ』は、Nintendo Switch 2における最初の“キラータイトル”と呼ぶにふさわしい実力を備えています。単に新しいだけではなく、しっかりと“未来を感じさせる体験”が詰まっている。それはグラフィックの進化にとどまらず、ゲームプレイそのものの発想が前へと進んでいるからこそ生まれるものです。
シリーズファンにとっても、これまでのイメージを良い意味で裏切ってくれる一本ですし、これが初めてのドンキーコング作品という人にとっても、“最高の入口”になる作品だと思います。まさに任天堂の底力を感じる一作。このタイトルが次世代のスタンダードを作っていく——そう思わせてくれる強さが『ドンキーコング バナンザ』には確かにあります。
