『Never7 -the end of infinity-』は、2000年に登場した恋愛アドベンチャーゲームでありながら、後のInfinityシリーズの基盤を築いた記念碑的な作品です。物語は、大学ゼミの合宿で離島を訪れた主人公・石原誠が、そこで体験する奇妙な出来事から始まります。それは「4月6日に必ず誰かが事故で命を落とす」という避けられない運命のような予知夢で、プレイヤーは誠として何度もその未来を変えようと試みるのですが、選択肢をどう選んでも結末は悲劇へと収束していきます。この繰り返される運命が、作品全体を支配する“無限ループ”の仕掛けになっているのです。
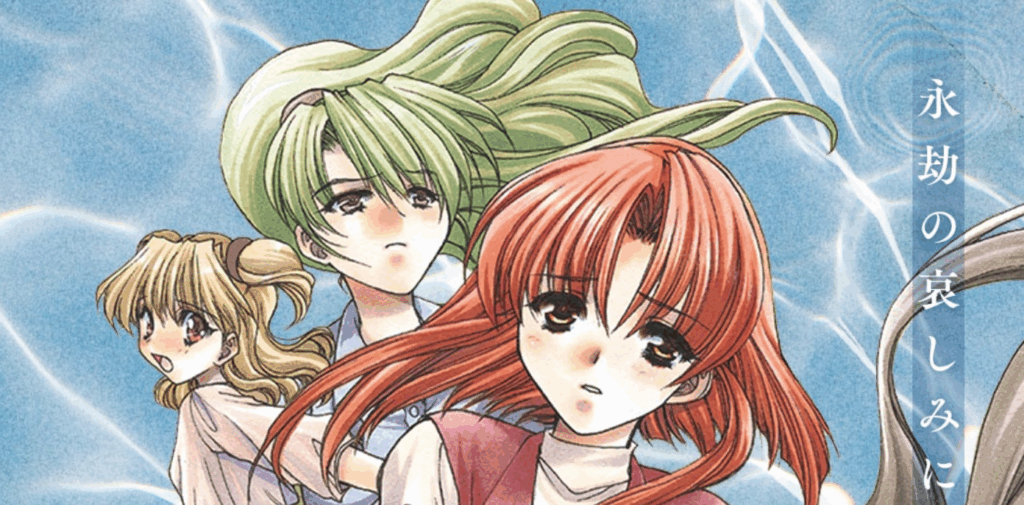
初めて触れる人は「時間を巻き戻すループものの恋愛ゲームかな」と思うかもしれません。ただ、この作品の面白さは単なるループ設定にとどまらず、物語の深部で明かされる「キュレイシンドローム」という独自の理論に集約されています。強く抱いた妄想が現実に作用するという奇妙な概念が、物語の土台に据えられているのです。つまりプレイヤーが信じてきた“時間のループ”は、実際には主人公の精神に作用した妄想の産物であり、その現実感がひとつの世界を形作っているという仕掛けになっています。
しかも、この設定は後に続くInfinityシリーズでも作品全体を貫くテーマとして再登場していきます。そのため、『Never7』を振り返ることはシリーズ全体の成り立ちを理解することにもつながるのです。恋愛ADVというジャンルに属しながらも、プレイヤーは読み進めるうちに「これはただの恋愛ゲームではない」と強く感じさせられます。キャラクターたちの背景や心理描写も徹底されており、彼らが抱えるトラウマや葛藤が物語の謎と密接に絡んでいるからこそ、読後に深い余韻を残す作品となっているのです。
避けられない死と繰り返される運命――『Never7』物語の概要
『Never7』の物語は、一見すると大学生活の延長のような平和な合宿から始まります。主人公・石原誠は、仲間たちとともに離島を訪れ、何気ない日常の中で友情や恋愛のきらめきを体験するのですが、その穏やかさはすぐに不穏な影に覆われていきます。誠が体験するのは、必ず4月6日に誰かが死ぬという悪夢のような出来事で、それはただの夢ではなく現実と地続きのものとして繰り返されていくのです。プレイヤーは幾度もその未来を変えようと試み、選択肢を選んで行動を重ねますが、結果として待ち受けているのは必ず悲劇。彼女を救おうとする度に運命は姿を変え、しかし最後にはまた同じ結末へと収束していきます。
こうした仕掛けは、プレイヤーに強烈な無力感とともに「なぜ同じ運命が繰り返されるのか」という疑問を抱かせます。普通の恋愛ゲームであれば、選択肢を正しく選べばヒロインは救われ、幸福なエンディングにたどり着くものです。けれど『Never7』ではその期待が裏切られ、どのルートでも結局は“死”という避けられない終着点が待ち構えています。そのため、物語を進めれば進めるほどプレイヤーは作品に仕掛けられた謎の深みへと引き込まれていくのです。
さらに印象的なのは、繰り返される運命を彩る小道具の存在です。合宿先のロッジで耳にする「ベルの鈴の音」がその象徴であり、ループの始まりを告げる合図として毎回登場します。一見すると何気ない演出のようでありながら、実は後に明かされる真相の伏線として重要な役割を担っているのです。誠が直面するループは単なる時間のやり直しではなく、もっと複雑で、もっと根源的な謎に結びついていることをプレイヤーに暗示しているのです。
妄想が現実を侵食する――物語を動かす謎の正体
『Never7』を語る上で避けて通れないのが「キュレイシンドローム」という独自の概念です。普通のループものでは、時間そのものを巻き戻したり、異なる世界線を行き来したりする設定が一般的ですが、本作ではそうした理屈では説明できない不思議な現象が物語を支配しています。プレイヤーが信じていた“時間の繰り返し”は、実は主人公の精神に作用した妄想が現実化する力によって引き起こされていたのです。この異様な仕組みが、物語のすべての不可解さを裏から支えていることが次第に明らかになっていきます。
キュレイシンドロームの恐ろしさは、ただの思い込みや幻覚にとどまらない点にあります。強く抱いた妄想は本人だけでなく周囲の人間を巻き込み、さらには物理法則さえ歪めて現実を作り変えてしまうのです。つまり、登場人物たちが体験する不条理や事件の数々は、科学で説明できるタイムトラベルではなく、妄想が形を持って現れた“もう一つの現実”として描かれているのです。こうした大胆な設定はプレイヤーを混乱させつつも、物語への没入感を強める仕掛けとして大きな役割を果たしています。

そして、このシンドロームを裏付ける象徴的な存在が「ベルの鈴」です。合宿所で毎回聞こえるその音は、単なる雰囲気づくりではなく、主人公が妄想の世界――つまり“キュレイ空間”へ足を踏み入れたことを示す合図でもあります。何気ない演出に見える鈴の音が、実は現実と虚構を隔てる境界線だったと知った時、プレイヤーはこれまで体験してきた物語のすべてを改めて考え直すことになるのです。ループを繰り返すたびに深まる違和感と、その背後で静かに進行する妄想の現実化。この二重構造こそが『Never7』を唯一無二の物語へと押し上げている大きな要因なのです。
交錯する過去と宿命――キャラクターたちが背負うもの
『Never7』の魅力を語るうえで欠かせないのが、登場人物たちが抱える背景です。表面的には明るく個性豊かなキャラクターが揃っているように見えますが、その裏には深いトラウマや宿命が隠されており、物語の進行とともに少しずつその素顔が露わになっていきます。単なる恋愛対象として描かれているのではなく、それぞれが物語の核心に直結する存在として配置されている点が本作の大きな特徴でもあります。

たとえばヒロインの一人である樋口遙。彼女は最初こそごく普通の少女のように振る舞いますが、物語が進むにつれてその正体に疑問が生じていきます。最終的に示されるのは、彼女自身が強い思念によって生まれた「思考実体」である可能性でした。つまり遙は、肉体を持つ人間ではなく、キュレイシンドロームが作り出した“存在するはずのない存在”だったのです。彼女がときおり現実感を欠くように描かれる場面は、その真実を示唆する伏線でもありました。
一方で守野くるみは、幼少期に誘拐事件に巻き込まれ、その際に背中に大きな火傷を負った過去を持っています。普段は明るく振る舞い、無邪気さで場を和ませる彼女ですが、その裏には人前で肌を見せることを極端に恐れる心の傷が存在しています。そのギャップが彼女の言動に奥行きを与え、プレイヤーに強い印象を残すのです。
そして川奈ゆうか。彼女は裕福な家庭に育ちながらも、心の奥底では消えない葛藤を抱えています。実は彼女の正体は守野くるみのクローンであり、その事実がゆうか自身の存在意義を揺るがしていました。常に「自分は代用品に過ぎないのではないか」という不安を背負いながら、それでも一人の人間として生きようとする姿が彼女のルートを通して描かれます。ここで提示されるテーマは「オリジナルとコピー」という重い問いであり、物語に人間的な深みを与えているのです。
さらに忘れてはならないのが、いづみという人物の存在です。彼女は大学院生であり、物語全体の黒幕的な役割を果たしています。いづみが計画していたのは、キュレイシンドロームの存在を否定するための「反証実験」でした。しかしその実験は予想に反して成功してしまい、むしろシンドロームの現実性を証明してしまう結果を招きます。科学者としての合理性と弟への複雑な感情、その二つの軸がいづみというキャラクターを強烈に際立たせているのです。
このように、各キャラクターの背景は単なる設定ではなく、物語の根幹に直結しています。プレイヤーは彼らの苦悩や葛藤に触れることで、ループの謎やキュレイシンドロームの恐ろしさをより深く理解していくことになるのです。
二重三重のどんでん返し――真相ルートが明かす衝撃の結末
『Never7』を最後まで進めたプレイヤーが直面するのは、予想をはるかに超えた真実です。繰り返されるループの正体、そして主人公の存在そのものに隠されていた仕掛けが、真相ルートによって一気に解き明かされていきます。特に「いづみキュア」と呼ばれるシナリオは、物語全体を覆っていた謎を科学的視点から暴き出す役割を持ち、プレイヤーが信じてきた“物語の土台”を根本から揺さぶります。
このルートで語られるのは、いづみが実行していた「反証実験」の全貌です。彼女は非科学的とされるキュレイシンドロームを否定するため、弟である石動イツキを被験者に選び、偽りの人格「石原誠」を植え付けました。プレイヤーが操作してきた主人公は、その実験の産物でしかなく、存在そのものが作られた人格だったという事実が突きつけられるのです。この瞬間、プレイヤーは自分が操っていたキャラクターが実は幻にすぎなかったことを理解し、強烈な虚脱感に包まれることになります。
さらに「優夏キュア」と呼ばれるシナリオでは、科学的な説明にとどまらず、登場人物たちの心理的な側面から事件の裏側が語られます。各キャラクターがどんな思いを抱えていたのか、表には見えなかった心の揺らぎが明かされていくことで、プレイヤーは物語をより多角的に理解できるようになるのです。この二つのシナリオは互いに補完し合い、一方だけでは決して辿り着けない深みにプレイヤーを導いていきます。
そして最後に突き付けられるのが、イツキが誠という虚構の人格から解放され、現実に戻っていくという結末です。そこに待っていたのは、ループを終わらせる歓喜ではなく、妄想と現実の境界を歩いてきた彼自身の覚醒でした。プレイヤーは、この物語全体が一つの壮大な実験であり、自分が信じてきた物語すらも仕掛けの一部だったという感覚に打ちのめされるのです。単なるゲームの結末ではなく、プレイヤーの心に深く刻まれる衝撃的な体験こそが『Never7』最大の魅力だといえるでしょう。
衝撃と余韻――『Never7』が残したもの
『Never7』を体験したプレイヤーに残るものは、ただのエンディングの記憶ではありません。繰り返されるループの先に待ち構えていたのは、主人公の正体に関する衝撃的な真実であり、その真相を知った瞬間にそれまで積み上げてきた物語のすべてが裏返されてしまいます。プレイヤーは自分が信じていた物語の枠組みを壊され、改めて“物語とは何か”を問い直されるのです。この強烈な体験こそが、『Never7』が単なる恋愛アドベンチャーの枠を越え、今なお語り継がれる理由になっています。
また本作は、Infinityシリーズの幕開けを告げる作品でもあります。後に続く『Ever17』や『Remember11』は、それぞれが異なるテーマを持ちながらも、「キュレイシンドローム」をはじめとする独自の設定を共有し、シリーズ全体に連続性を与えています。その意味で『Never7』は、一つの作品でありながら後の物語世界を広げていくための起点でもありました。初めて遊んだときの衝撃がそのまま次の作品への期待へとつながり、シリーズ全体を追いかけたくなる動機を作り出していたのです。
そして忘れてはならないのが、各キャラクターたちが見せた人間的な弱さや葛藤です。遙の存在は妄想の具現化そのものを体現し、くるみやゆうかは過去の傷や生まれ持った宿命を抱えながらも必死に生きようとしました。彼女たちの苦悩や選択は、単なる設定を越えてプレイヤーの心に重く響きます。だからこそ、『Never7』はゲームを終えた後も長く心に残り、ふとした瞬間に思い返したくなる物語になっているのです。
結末に至るまでの仕掛けは緻密でありながら、その全体像は一度プレイしただけでは理解しきれないほど複雑です。けれど、その複雑さがあるからこそ再びプレイしたときに新しい発見があり、時間をかけて噛み締められる奥深さを備えています。プレイヤーは“ただ一度体験するだけでは終わらない”物語に触れた実感を抱き、そこで得た余韻が心の奥に長く残り続けるのです。
